寒中見舞いはいつからいつまで?出す時期が過ぎたらどうしたらいいのか?
「ニュースで今年は雪が多いって言ってたけど、北国に住む〇〇さんは元気なのかしら・・」
「今年は喪中で年賀状が出せないけど、ご挨拶はしたいな・・」
「年賀状を出していない相手から年賀状が届いたから今からでも年賀状出した方がいいよね?」
このような時、あなたならはどうしますか?年賀状を出しますか?・・答えは、不正解です。
上記3つの場合、出すべきなのは「寒中見舞い」です。
しかしこの寒中見舞い、「暑中見舞いはよく聞くけど、寒中見舞いは初めて聞いた」という人がいるようで、以外に存在そのものを知らないという方が多く、また知っていたとしても出し方や使い方を間違っている場合もあるようです。
では、そんな寒中見舞いとは一体どのようなものなのでしょうか。
寒中見舞いを出す時期はいつからいつまでか?

寒中見舞いとは?
寒中見舞いは、新年の挨拶が終わった後、まだ冬の寒さが厳しい時期に、親しい人々へ健康や幸福を願って送るハガキや手紙のことです。
この風習は、日本の四季を大切にする文化の中で生まれたもの。
冬の寒さを乗り越え、新しい年を元気に過ごしてほしいという願いが込められています。
寒中見舞いを送るベストな時期
寒中見舞いを送る最適な時期は、一般的には1月5日か6日から2月4日頃までです。
この期間は、「小寒」と「大寒」と呼ばれる、一年で最も寒い時期にあたります。
特に、1月1日から7日までの「松の内」が終わってから送るのが一般的。
松の内が明け、新しい年が始まった後に、寒さに負けず頑張っている人たちへの応援のメッセージを送るのが良いでしょう。
送るタイミングの目安
| ご希望の到着日 | 送るべき日付 |
|---|---|
| 1月7日 | 1月5日か6日 |
寒中見舞いの期間の終わり
寒中見舞いの期間の終わりは、「立春」を目安にします。
立春は節分の翌日、2月4日に訪れるので、それを過ぎると「余寒見舞い」となります。
時期を間違えないように注意しましょう。
寒中見舞いの魅力
寒中見舞いは、寒い冬に心温まるメッセージを送る、日本の美しい習慣の一つです。
大切な人たちに、健康と幸せを願う言葉を添えて、この冬も暖かい気持ちを分かち合いましょう。
手書きのハガキや手紙で、あなたの心からの思いやりを伝えることができます。
デジタルが溢れる現代だからこそ、手書きの温もりが人の心をぐっと引き寄せるのです。
寒中見舞いを通じて、寒い季節も心はぽかぽか。
大切な人への思いやりを形にして、素敵な冬のひとときを過ごしましょうね。
寒中見舞いのハガキは何を使う?
寒中見舞いは、新年の挨拶を欠礼した方々への心遣いや、年始に会えなかった方への思いやりを伝える大切な手段です。
でも、どんなハガキを選べばいいのか、迷うこともありますよね。
まず、寒中見舞いに使うハガキですが、日本郵便が発行する官製はがきが一般的です。
この官製はがきには、ヤマユリ、山桜、胡蝶蘭の三つのデザインがあります。どのデザインを選んでも基本的には問題ありませんが、送るシーンによっては、選ぶデザインによって相手に与える印象が変わることもあるんです。
特に、年賀状を出せなかった「喪中」の方や、年賀欠礼の報告を兼ねた寒中見舞いを送る場合には、胡蝶蘭のデザインが最適です。
胡蝶蘭は、その落ち着いた美しさで、お悔やみのシーンにもふさわしく、失礼にあたることがありません。
一方、ヤマユリや山桜のデザインは、その華やかさから、喜びや祝福の気持ちを表現するのに適しています。
ですから、喪中の方には少し華やかすぎるかもしれませんね。
それでは、どのデザインをいつ使うのが良いのか、簡単な表でまとめてみました。
| デザイン | 特徴 | おすすめの使用シーン |
|---|---|---|
| ヤマユリ | 華やかで明るい | 喜びや祝福を伝えたい時 |
| 山桜 | 春らしい、爽やか | 春の訪れを感じさせる時 |
| 胡蝶蘭 | 落ち着いた美しさ | 喪中やお悔やみの時 |
寒中見舞いは、寒い季節に相手の健康を気遣うとともに、心を込めたメッセージを伝える大切な手段です。
選ぶハガキ一枚にも、その心遣いが表れるもの。
ぜひ、相手のことを思いながら、最適なデザインを選んでくださいね。
寒中見舞いを出すときはどのような時?

どのような時に寒中見舞いを出すのが適切なのでしょうか。
ここでは、その3つの主なケースを、より詳しく、ご紹介します。
1. 豪雪地帯の方への体調の気遣い
寒さが厳しい地域にお住まいの方への心遣い
- 背景: 日本には豪雪地帯が多く、冬は特に厳しい寒さに見舞われます。
- 目的: このような地域にお住まいの方々へ、寒さへの耐え忍びや体調を気遣うメッセージを送ることが、寒中見舞いの大切な役割です。
- 特徴: 年賀状とは異なり、もっと個人的で、心からの暖かいメッセージを込めることができます。
2. 喪中はがきの代わりに
喪中の方への配慮深い挨拶
- 背景: 喪中の方は、新年の挨拶として年賀状を出すことが避けられます。
- 目的: そんな時、寒中見舞いは、故人を偲びつつ、生きている私たちの絆を大切にする方法として用いられます。
- 応用: 年賀状を送ってしまった相手に対しても、寒中見舞いを通じて心からの思いやりを示すことができます。
3. 年賀状の代わりに
年始の挨拶を忘れた時の救いの手
- 背景: 年賀状は通常、1月7日までに交換されますが、時にはうっかり忘れてしまうことも。
- 目的: 寒中見舞いは、そんな時に年賀状の代わりとして、新年の挨拶を伝える素敵な方法です。
- ポイント: 年賀状を出し忘れたことへの謝罪の言葉を添えることで、より心のこもったメッセージになります。
寒中見舞いは、ただの挨拶以上の意味を持ちます。
それは、寒い季節にお互いの心を温め合う、日本の美しい文化の一つです。
この伝統を通じて、私たちは家族や友人、知人への深い愛情や思いやりを表現することができるのです。
寒中見舞いの基本的なマナー
寒中見舞いの基本構成
- お見舞いの挨拶
「寒中見舞い申し上げます」や「寒中お見舞い申し上げます」といったフレーズで始めます。この言葉一つで、寒い冬に相手のことを思っている気持ちが伝わります。 - 相手の健康を気遣う言葉、近況報告
「寒さが厳しい日が続きますが、お体にはくれぐれもお気をつけください」といった言葉で、相手の健康を気遣いましょう。また、自分の近況を簡単に報告することで、親しみを込めたコミュニケーションが図れます。 - 相手の健康を祈る言葉
「今年一年、健康で穏やかな日々が続きますように」といった言葉で、相手の健康と幸せを祈ります。 - 日付
寒中見舞いは、通常、立春(2月4日頃)までに送るのが一般的です。日付は、送る日のものを記載します。
状況に応じたマナー
- 年賀状をもらった場合
年賀状をいただいた方へは、そのお礼の言葉を添えましょう。「年始にお送りいただいた年賀状、ありがとうございました」という一文が、相手への感謝の気持ちを伝えます。 - 自分が喪中の場合
喪中であることを伝え、「新年のご挨拶を差し控えさせていただきました」と一言添えると良いでしょう。 - 相手が喪中の場合
相手が喪中であれば、お悔やみの言葉を添え、「この冬のご健康をお祈りしております」といった配慮のある言葉を選びましょう。
はがきの選び方
寒中見舞いは、通常の郵便はがきや私製はがきを使用します。年賀はがきは避けましょう。市販されている寒中見舞い専用のはがきもあり、季節感あふれるデザインのものを選ぶと、より心が伝わります。
寒中見舞いは、寒い冬に相手を思う温かい心を伝える大切な文化です。このマナーを心に留めて、心温まるメッセージを届けましょう。
寒中見舞いの例文
寒中見舞いのはがきには、特定の要素を含めることが重要です。ここでは、その要素を詳しく説明し、さらに具体的な例文をご紹介します。
寒中見舞いのはがきに含めるべき5つの要素
- 季節のあいさつ:季節の変わり目を感じさせる言葉で、相手に対する思いやりを表現します。
- 時候の挨拶:現在の季節や天候にちなんだ挨拶で、相手への気遣いを示します。
- 年賀状のお礼や欠礼のお詫び、または近況報告:年始の挨拶を交わしたことへの感謝、またはそれができなかった場合のお詫び、さらには自分や家族の近況を伝えます。
- 挨拶:相手への敬意や感謝の気持ちを込めた言葉を選びます。
- 日付:はがきを書いた日付を記載します。
具体的な例文
例文1
「寒中お見舞い申し上げます。今年は暖冬と言われていますが、それでも冬の寒さは身にしみますね。皆様のご健康と暖かい日々を心から願っております。我が家は皆、風邪一つひかずに元気に過ごしています。この時期、流行するインフルエンザには十分お気をつけください。どうぞお身体を大切になさってくださいね。」
例文2
「寒中お伺い申し上げます。今年の冬は暖かい日が続いていますが、朝晩の冷え込みはやはり厳しいですね。どうか無理をせず、温かくしてお過ごしください。私たち家族は、皆健康で毎日を楽しく過ごしています。春の訪れももう間近です。新しい季節が皆様にとっても素晴らしいものとなりますように。くれぐれもお体を大切にしてください。」
寒中見舞いを出し忘れたらどうしたらいいのか?
「寒中見舞いを忘れたらどうしよう?」というお悩み、よくあることですよね。
私たちの忙しい日常では、ついつい大切なことを見落としてしまうこともあります。
でも、ご安心ください。
寒中見舞いを出し忘れた場合でも、素敵な方法でフォローすることができるんですよ。
余寒見舞いって?
まず、余寒見舞いとは何かをご説明しましょう。
立春が過ぎ、カレンダー上では春が始まったとされていますが、実際の気候はまだひんやりとしていますよね。
そんな時期に、相手の健康を気遣う心温まるメッセージを送るのが「余寒見舞い」なんです。
いつ送るの?
余寒見舞いは、一般的に立春の翌日から2月末日までに送ります。
今年の立春は2月4日ですから、2月5日から2月末日までが送る適切な期間となります。
どんな内容を書くの?
内容は、寒中見舞いと同様に、相手の健康を気遣う言葉を中心に、心からのメッセージを添えましょう。
例えば、「まだ寒い日が続きますが、どうぞお体を大切になさってくださいね」といった感じです。
個人的な近況を少し加えるのも良いでしょう。
余寒見舞いの書き方
- 挨拶:まずは暖かい挨拶から始めましょう。
- 健康への気遣い:「寒さが厳しいこの時期、どうぞお体を大切に」といった言葉を添えます。
- 個人的なメッセージ:近況報告や、相手への感謝の気持ちを伝えるのも素敵です。
- 締めの言葉:「これからも変わらぬお付き合いを」といった言葉で締めくくります。
余寒見舞いのポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送る時期 | 立春の翌日から2月末日まで |
| 挨拶 | 暖かく、心からの挨拶を |
| 中身 | 相手の健康を気遣う言葉、個人的な近況 |
| 締めくくり | 今後の関係を大切にする言葉で |
余寒見舞いは、寒中見舞いを忘れてしまった時の救世主のようなもの。
この機会に、心からの言葉で大切な方々に思いやりを伝えてみてはいかがでしょうか。
きっと、あなたの温かい心が伝わり、より深い絆を築くことができるはずですよ。
寒中見舞いと年賀状の違いは?

日本の伝統的な挨拶文化には、年賀状と寒中見舞いという二つの大切な要素があります。
これらは一見似ているように思えますが、実はそれぞれに独特の意味とタイミングがありますので、それぞれについて詳しくご紹介しましょう。
年賀状:新年の挨拶と感謝の気持ちを込めて
年賀状は、新年を迎えるにあたり、お互いの無事と幸福を祈り、また前年中の感謝の気持ちを伝えるために送られるはがきです。
この習慣は、なんと平安時代にまで遡ることができ、その歴史の深さには驚かされます。
もともとは手書きの手紙でしたが、1873年に郵便はがきが導入されてからは、これを使って年賀状が送られるようになりました。
年賀状には、新年の挨拶の言葉と共に、家族の近況報告や前年の感謝の気持ちを綴ります。
また、年賀状には縁起の良い絵や言葉を添えることが一般的で、受け取った人にとっても新年の喜びを感じることができる素敵な文化です。
寒中見舞い:寒さの中での気遣い
一方、寒中見舞いは、年賀状とは異なり、新年が始まってから、特に寒さが厳しい時期に送られるはがきです。
これは、寒い季節に相手の健康や安全を気遣うという意味合いが強く、1月5日以降、立春の2月4日までの間に送るのが一般的です。
寒中見舞いは、年賀状を送り忘れた場合や、年始に不幸があった家庭に対しても配慮を示すために用いられます。
また、2月4日を過ぎてから送る場合は「余寒お見舞い」と称し、こちらは2月下旬頃まで出すことができます。
| 種類 | 送る時期 | 目的 |
|---|---|---|
| 年賀状 | 新年前 | 新年の挨拶、前年の感謝 |
| 寒中見舞い | 1月5日〜2月4日 | 寒さへの気遣い、年賀状のフォローアップ |
| 余寒お見舞い | 2月4日〜2月下旬 | 寒さの続く期間の気遣い |
これらの伝統的な挨拶方法は、日本の文化の中で大切にされており、年始のコミュニケーションを豊かにしています。
お互いの安全と健康を願い、感謝の気持ちを伝えるこれらの習慣は、今後も大切に受け継がれていくことでしょう。
寒中見舞いを出す時期はいつからいつまでか?のまとめ
寒中見舞いは、相手への気遣いを込めたものとなります。
年賀状とは別に毎年送られている方がいる一方で、寒中見舞いそのものを知らない方もいらっしゃるようなので、是非これを機会に知って頂けたらと思います。
年賀状の関連記事
年賀状の返信不要を相手に伝える時の書き方や例文!相手に失礼?
年賀状の数字の縦書きの書き方!漢数字のほうがいい?区切るところは?
年賀状の横書きの宛名は失礼にならない?正しい書き方やマナーは?
年賀状での御一同様の使い方!家族や会社向けで連名を使う場合は?
年賀状の裏に差出人の住所を書くのはOK?縦書き横書きどっちが正しい?
喪中の人に年賀状を出しても大丈夫?知らずに出してしまった時は?
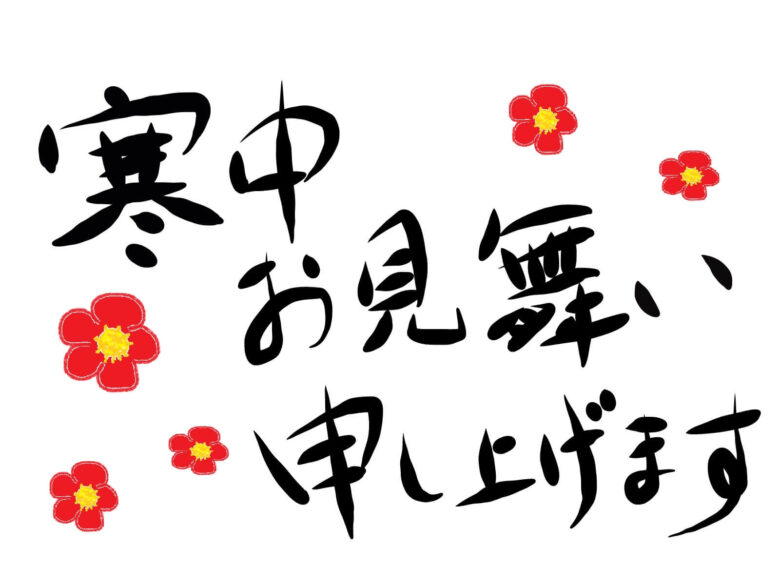

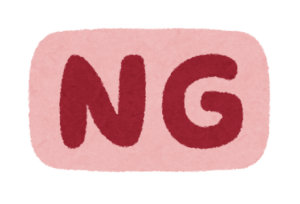






コメント