先負の七五三は大丈夫?縁起は悪くない?
先負の日に七五三を予定しているあなた、ちょっと待ってください。
『先負』と聞くと、なんとなく足踏みしてしまいますよね。
でも、大切なお子様の成長を祝う七五三、実は先負の日が縁起悪いというのは誤解かもしれません。
そもそも六曜は中国から伝わったもので、日本の神社とは無関係。午前中は避けて、午後からのお参りなら問題なし、なんて言われています。
では、本当に先負の日は避けるべきなのでしょうか?
それとも、もっとリラックスして計画を立てても良いのでしょうか?
今日は、そんな疑問を解決するために、先負の七五三について、おすすめの時間帯や、もっと気軽に楽しめるコツをご紹介します。
先負の日に七五三は避けたほうがいい?
日々の暮らしの中で「先負」という言葉を耳にすると、どこかで心がぴりっと緊張するものですよね。
その名の通り、何かと縁起が悪いように思えてしまうかもしれません。
でも、そんな先負の日にちょっとした知識を添えると、意外とチャーミングな一面が見えてくるんですよ。
さて、「先負」とは、実は古くから伝わる六曜の一つで、「先んずれば必ず負ける」という意味が込められています。
この日は、朝のうちには何かとトラブルが起こりやすいとされているため、午前中は特に慎重に行動するのが賢明とされています。
しかし、午後になると運気が上昇し、「吉」とされるので、午後からの行動は吉とされているんですよ。
では、大切なお子様の成長を祝う「七五三」のお参りは、先負の日に避けた方がいいのでしょうか。
実は、そこにはちょっとした誤解があるんです。
六曜は中国から伝わった暦の一部であり、日本の神社とは全く関係がないのです。
ですから、もしも予約をしてしまったとしても、心配することはありません。
それに、七五三は、そもそもは11月15日に行うのが伝統的なんです。
この日付には、徳川綱吉が長男の成長を祝ったとされる歴史的背景があるのですが、現代では11月15日を中心に前後一ヶ月の間にお参りをするのが一般的になっています。
そのため、縁起を担ぐ方々は、大安や友引などの吉日を選ぶ傾向にありますが、必ずしもそれに囚われる必要はないのです。
七五三は、お子様の健やかな成長を祝い、家族の絆を深める素敵な行事。
どんな日に行うにせよ、その日は家族にとって特別な一日になることでしょう。
それでは、先負の日に七五三を行う際のポイントを、表にまとめてみました。
| 六曜 | 午前の運勢 | 午後の運勢 | 七五三のお参り |
|---|---|---|---|
| 先負 | 凶とされる | 吉とされる | 問題なし |
この表を見ていただければ分かる通り、先負の日が七五三のお参りに影響を与えることはないんです。
大切なのは、お子様の成長を心から祝福し、家族でその瞬間を共有すること。
そんな温かい気持ちが、どんな日にも幸せを運んでくれるはずです。
だから、もし先負の日にお参りを予定しているなら、朝はゆっくりと準備をして、午後からの吉時間に神社へと足を運びましょう。
お子様の晴れやかな晴れ姿を見守る家族の笑顔が、何よりの祝福となるはずですよ。
先負の日の七五三の時間帯はいつがいいの?
日本の伝統に根差した行事の一つに、子どもの成長を祝う七五三があります。
この大切な日に、最良の時間帯を選ぶことは、多くの親御さんにとって重要な課題です。
特に、先負の日に七五三を行う場合、そのタイミングは一層慎重に選ばれるべきでしょう。
先負とは、六曜の一つで、文字通りには「先に負ける」という意味を持ちます。
この言葉から連想される通り、一見すると不吉な日と捉えがちですが、実はそうではありません。
先負は、大安や友引、先勝に次ぐ吉日とされており、日の半分は実は吉とされる時間帯を含んでいるのです。
では、七五三において先負の日を選ぶ際、どの時間帯が適しているのでしょうか。
先負は午前中を凶とし、午後からは運気が上昇し吉となるとされています。
したがって、午後の時間帯は、縁起を担ぐ親御さんにとっても安心してお参りを行える時間帯と言えます。
しかし、伝統的には、七五三を含む神事は午前中に行うのが良いとされ、午前中にお参りを済ませることで、午後は家族でのんびりと過ごす時間を持てるというメリットがあります。
そのため、午前中に七五三を行いたいと考える方も少なくありません。
午前中にお参りを避けたい場合は、先負の午後がおすすめです。
午後は神社も比較的空いており、小さなお子さんを連れてのお参りもスムーズに行えます。
また、朝の忙しさを避け、ゆったりと準備をすることができるのも魅力です。
以下の表に、先負の日の七五三における時間帯別のメリットをまとめました。
| 時間帯 | メリット |
|---|---|
| 午前中 | ・伝統的に良いとされる時間帯
・午後の自由な時間が増える |
| 午後 | ・人出が少なくなる
・準備に余裕を持てる ・午前中の凶を避けられる |
最終的には、ご家族の都合やお子さんの体調を最優先に考え、最も良いと思われる時間帯を選ぶことが大切です。
大切な家族の一員の成長を祝う七五三。先負の日でも、吉となる時間帯を見極め、素敵な一日を過ごしましょう。
七五三の前撮りに最適な日は?気になるタブーとは?
七五三と聞くと、多くの方が華やかな着物や袴に身を包んだ子どもたちの姿を思い浮かべることでしょう。
この日本古来の節句は、子どもたちの成長を祝い、健やかな将来を願う大切な行事です。
しかし、実際のお祝いの日は、準備や移動で忙しく、ゆっくりと写真を撮る時間が取れないことも少なくありません。
そこで注目されているのが「前撮り」という選択肢です。
前撮りとは、文字通り七五三の本番前に行う写真撮影のこと。
この日を選ぶ際、多くのお父様やお母様は、吉日を選ぶよりも、お子様の体調や気分を最優先に考える傾向にあります。
では、前撮りの日程を決める際に、先負の日は避けるべきなのでしょうか?
前撮りの日程選びのポイント
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| お子様の体調 | 何よりもお子様が元気である日を選びましょう。 |
| お子様の機嫌 | 撮影当日は長時間の撮影になることも。お子様が最もご機嫌な時間帯を見計らって。 |
| 気候 | 撮影は屋外で行うことも多いため、穏やかな秋の日を選ぶのがおすすめです。 |
| 平日・休日 | 園や学校を休ませることなく、家族の予定が合う日を選びましょう。 |
前撮りにおける先負の日の扱い
前撮りの日程を決める際に、先負の日を避ける必要はありません。
お子様がリラックスして自然な笑顔を見せてくれる日が最適です。
また、撮影スタジオや写真館の予約状況を考慮し、ご家族にとって都合の良い日を選ぶことが肝心です。
七五三の前撮りは、お子様の成長を記録する大切な瞬間です。
先負の日であっても、お子様のペースを大切にし、家族みんなが楽しめるような日程を選びましょう。
最終的には、お子様の輝く笑顔が一番の宝物となるはずです。お子様の特別な一日を、心に残る素敵な思い出として刻みましょう。
七五三のお参りにぴったりな日を選ぶコツ
子どもたちの成長を祝う七五三。この大切な節目には、お参りの日取り選びも重要な役割を果たします。
そこで、日本古来の暦、六曜を参考に、最適な日を見つけましょう。
大安
大安は、六曜の中でも特に縁起が良いとされる日です。
結婚式や入籍、お宮参りなど、人生の節目に選ばれることが多いこの日は、七五三のお参りにも最適。
一日中、どの時間帯も吉とされているため、ご家族のスケジュールに合わせて自由に予定を立てることができます。
友引
大安の次に吉日のため、大安と並んで予約がとりにくい日となっています。
昼間の11時から13時の間だけは凶とされているため、この時間帯は避けた方が良いでしょう。
午前中早めや、午後遅めの時間帯であれば、お参りに適しています。
先勝
「先んずればすなわち勝ち」の意味で、早くに行動するのが吉となることから、午前中が吉、午後からは凶となります。
先負とは反対の吉凶です。
午前中にお参りを済ませてしまいたいという場合は、先勝を選ぶのがよいでしょう。
これらの情報を踏まえ、七五三のお参りに最適な日を選ぶ際の参考にしてください。
大切なお子様の一大イベントを、最良の日に祝いましょう。
以下の表は、六曜における吉凶の時間帯をまとめたものです。お参りの計画を立てる際にご活用ください。
| 六曜 | 吉の時間帯 | 凶の時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大安 | 終日 | なし | どの時間帯も安心してお参り可能 |
| 友引 | 昼以外 | 11時~13時 | 昼間は避け、午前か午後遅めが良い |
| 先勝 | 午前中 | 午後 | 朝早めにお参りを済ませるのが吉 |
七五三のお参りは、お子様の健やかな成長を願う大切な行事です。
六曜を参考にしながら、家族にとって最適な日を選び、心に残る一日を過ごしてくださいね。
七五三で六曜は気にしたほうがいいの?
まず、六曜とは何かというところから始めましょう。
六曜とは、元々は中国からやってきた暦の注に関するもので、私たちの日常にも馴染み深い「大安」や「友引」などの言葉がそこに含まれています。
これらは、日々の吉凶を占うために使われてきましたが、その起源は賭け事を好む中国の人々が、運勢を占うために考え出したものだとか。
では、日本にはいつ伝わったのでしょう?それは鎌倉時代末期から奈良時代にかけてのこと。
しかし、六曜が一般に広く認知されるようになったのは、実は戦後からなんです。
つまり、六曜は日本古来からの風習というわけではなく、比較的新しい文化の一部と言えるでしょう。
さらに興味深いのは、六曜の名称や意味が時代と共に変わってきたこと。
例えば、現在では「大安」が最も吉とされる日ですが、かつては「先勝」がそれにあたり、「先負」も「小吉」や「周吉」と呼ばれ、今よりも良い日とされていたんですよ。
また、六曜の中には「仏滅」という言葉もありますが、これを聞くと仏教や神道との関連を想像しがちです。
しかし、実は六曜は仏教や神道とは直接の関係はないのです。
それでは、七五三のお祝いに六曜は関係あるのでしょうか?
結論から言うと、特に気にする必要はないと思います。
なぜなら、七五三はお子様の成長を祝う日であり、家族の幸せな時間を共有することが何よりも大切だからです。
ただし、もしも「六曜を気にすることで心に安心を得られる」という場合は、それも一つの良い方法です。
大切なのは、その日を迎える皆さんの心が穏やかであること。
六曜はあくまで参考の一つとして、お子様の晴れの日を心から楽しんでくださいね。
最後に、六曜についての小さな豆知識を一つ。
下記の表で、六曜の各日についての意味を簡単にまとめてみました。お役立ていただけると幸いです。
| 六曜 | 意味 | 現代での一般的な解釈 |
|---|---|---|
| 大安 | 吉日 | 何をするにも良い日とされています |
| 友引 | 半吉 | 結婚式などは良いが葬式は避けたい日 |
| 先勝 | 小吉 | 朝のうちに良いことがある日 |
| 先負 | 小凶 | 朝は避け、午後からが良い日 |
| 赤口 | 凶 | 昼間は避けたい時間帯がある日 |
| 仏滅 | 大凶 | 何をするにも避けたい日 |
七五三のお祝いにおいては、このような六曜の吉凶を参考にするのも一つの楽しみ方ですが、何よりも家族が揃ってお子様の成長を祝うことが最も大切です。
素敵な七五三になりますように。
七五三の日取りの決め方とポイントは?
七五三のお祝いは、お子様が健やかに成長されたことをお祝いし、これからのさらなる発展を願う大切な行事です。
この特別な日をどのように決めるかは、多くのご家庭で悩ましい問題の一つですね。
そこで、心温まる七五三の日を迎えるためのポイントを、少し掘り下げてご紹介したいと思います。
お子様の体調を最優先に
まず第一に、お子様が元気いっぱいで、その日を楽しめる状態であることが何よりも大切です。
風邪をひいていたり、体調がすぐれないときに無理をしてお参りをすると、せっかくの晴れの舞台が台無しになってしまいます。
お子様が最高の笑顔でいられる日を選びましょう。
家族のスケジュールを考慮
次に、ご家族全員が集まれる日を選ぶことも重要です。
おじいちゃん、おばあちゃんをはじめ、親戚の方々が参加される場合は、みんなの予定を調整する必要があります。
事前に家族会議を開き、皆の都合の良い日を探しましょう。
六曜の考慮は柔軟に
昔ながらの六曜を重んじる風習もありますが、現代ではその必要性は薄れつつあります。
大安や友引など、縁起の良い日を選ぶのも一つの方法ですが、お子様の体調や家族の都合を優先する柔軟な姿勢が求められます。
11月15日にこだわらなくても大丈夫
伝統的には11月15日が七五三の日とされていますが、現在では11月15日前後の一ヵ月間であれば、いつお参りしても良いとされています。
ですので、無理に一日にこだわらず、お子様とご家族にとって最適な日を選ぶ余裕があります。
祖父母の意見も尊重
祖父母の世代では、伝統的な日取りにこだわる方も少なくありません。
お祝い事は大安に行うべきという考え方も根強いです。
祖父母がお参りに同席される場合は、事前にしっかりと意見を交換し、納得のいく日取りを決めることが大切です。
七五三の日取りを決める際は、以下のポイントをおさえておくと良いでしょう。
- お子様の体調を最優先:お子様が健康で楽しめる日を選びましょう。
- 家族の予定を考慮:全員が参加できる日を見つけましょう。
- 六曜の柔軟な考慮:縁起を担ぐのも良いですが、無理は禁物です。
- 11月15日に固執しない:一ヵ月の間であれば、いつでもお祝いできます。
- 祖父母の意見を尊重:世代間の意見の違いを尊重し、話し合いましょう。
このように、七五三の日取りは、お子様の成長を祝う大切なイベントです。
家族の絆を深め、お子様のこれからを祝福する日として、最適な一日を選びましょう。
先負けの七五三のまとめ
お子さんの健やかな成長を氏神様にお礼に参る七五三は、できれば縁起のよい大安に行いたいと思う方が多いと思いますが、大安の予約は早くから埋まってしまい、なかなか希望通りになることはありません。
しかし、そもそも七五三の日取りは六曜にこだわる必要がなく、先負に七五三をしても問題ありません。
とは言え、年配者の中には大安にこだわる方も多いので、事前に連絡や打ち合わせをしておき、当日にトラブルにならないように配慮することが必要な場合もあります。
先負の関連記事
先負に安産祈願のお参りをすると縁起が悪い?戌の日と重なった場合は?
先負に法事をしても縁起は悪くない?六曜で避けたほうがいい日は?
先負に宝くじを購入すると当たらないのは本当?買う時間帯はいつ?
先負に契約ごとは縁起が悪い?不動産や車の契約するのは大丈夫?
先負が開業日でも大丈夫なの?開業日の決め方はどうしたらいい?









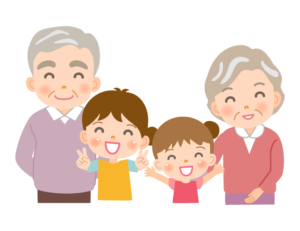


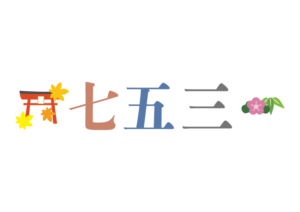


コメント