妊娠中の女性にとって、安産祈願は心の支え。
でも、「先負」の日にお参りするのは縁起が悪いと聞いて不安になる方も多いでしょう。
実は、先負の日の午後は吉とされ、安産祈願にも適しています。
また、戌の日との重なりについても、特に心配する必要はありません。
この記事では、そんな疑問を解消し、安心してお参りできる方法を紹介しています。
安産祈願の日取り選びに迷ったら、ぜひ参考にしてください。
先負に安産祈願をしても大丈夫?
「先負」と聞くと、どうしても「負け」という言葉に目が行ってしまいますよね。
でも、実はこの先負、午後にはちょっとした秘密が隠されているんです。
この先負、中国の古い暦注に由来する六曜の一つで、「先んずればすなわち負け」という意味を持っています。
これは、文字通りに解釈すると、午前中は何かと不運が重なりがち、でも午後になると運気が好転するという日なんですよ。
特に、安産祈願のような大切な行事には、日選びが重要視されますよね。
先負の日に安産祈願をする場合、午前中は避けて、午後に行うのがポイントです。
午後になると、先負の日も吉日の顔を見せるんです。
だから、午後の時間帯を選べば、安産祈願も吉兆を招くことができるのです。
では、なぜこのような変化があるのでしょうか。
実は、六曜の考え方には、一日の中で運気が変わるという独特の観点があるんです。
午前中は何かとトラブルが起こりやすいとされる先負ですが、午後になると運気が上昇し、良い流れに変わるとされています。
このように、先負の日は午後になると運気が上がるため、安産祈願を含む大切な行事にも適しているんです。
もちろん、安産祈願は心の準備や気持ちの問題も大きいので、自分が良いと感じる日を選ぶことが最も大切ですが、日取りに迷った時は、先負の午後を選ぶのも一つの良い方法かもしれませんね。
日本の伝統的な文化の中には、このように一見縁起が悪いように思える日でも、実は良い面を持っているものがたくさんあります。
大切なのは、その日の持つ意味を理解し、上手に活用すること。先負の午後のように、時には意外な吉兆を招くこともあるのですから。
先負に安産祈願へ行く時のオススメの時間帯
安産祈願に最適な時間帯について、優しく解説させていただきますね。
妊娠は女性にとって大切な時期、そして安産を願う気持ちは何よりも大切です。
そんな大切な時に、神社でのお参りはいつ行くのがベストなのでしょうか。
まず、一般的に神社でのお参りは、清らかな朝の時間帯がおすすめされています。
朝の空気は清々しく、新しい一日の始まりを感じさせますよね。
この時間は、穢れが少ないとされ、神様に願い事を伝えるには最適なのです。
朝の神聖な雰囲気の中で、心を込めて安産を祈ることで、その願いがより神様に届きやすくなると言われています。
しかし、午後のお参りには少し注意が必要です。
日中には様々な活動をするため、神社に行く前に他の場所に立ち寄ることもあるでしょう。
そうすると、神様に対して失礼にあたるとされています。
ですから、できれば午前中にお参りするのが良いとされているのです。
ただし、日本には六曜という独特の暦があり、特に「先負」という日には午後が縁起の良い時間帯とされています。
安産祈願をする際に、この六曜を考慮するのも一つの方法です。
ただ、妊婦さんの体調を最優先に考え、無理のない範囲でお参りする時間を選ぶことが大切です。
また、午後のお参りを選ぶ場合でも、日没間近の夕方は避けましょう。
この時間帯は「逢魔が時(おうまがとき)」と呼ばれ、昔から魔物が出るなどと言われています。
そんな時間にお参りするのは、あまり良いとは言えませんね。
このように、安産祈願には、清々しい朝の時間帯がおすすめですが、六曜を重視する場合は午後も選択肢に入ります。
大切なのは、妊婦さんの体調と心地よさを第一に考えること。
神様も、そんなあなたの心をきっと理解してくれるはずです。安産祈願の際は、この点を心に留めて、素敵な時間を過ごしてくださいね。
| 時間帯 | 特徴 | おすすめポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 午前中 | 空気が清々しく穢れが少ない | 神様に願いが届きやすいとされる | 特になし |
| 午後(六曜「先負」の日) | 先負の日は午後が縁起が良い | 縁起を重視する場合に適している | 他の場所に立ち寄らないようにする |
| 午後(六曜「先負」以外の日) | 一般的な日中の時間帯 | 体調に合わせて柔軟に設定可能 | 神様に失礼にならないよう注意 |
| 夕方(日没間近) | 逢魔が時と呼ばれる時間帯 | – | 魔物に出会うなどの言い伝えがあるため避ける |
安産祈願には「午前中」が一般的におすすめされていることが分かります。
清らかな朝の時間に神様に願いを伝えることで、その願いがより届きやすいとされています。
一方で、六曜の「先負」の日には午後が縁起が良いとされていますので、この日には午後のお参りも良いでしょう。
ただし、他の場所に立ち寄らずに直接神社へ行くことが望ましいです。
夕方の時間帯は、昔からの言い伝えにより避けた方が良いとされています。
特に日没間近の時間は、お参りには不向きとされているので注意が必要です。
このように、安産祈願のお参りには、時間帯を選ぶことが大切です。
妊婦さんの体調や信仰に合わせて、最適な時間を選んで、心穏やかなお参りをしてくださいね。
戌の日が先負でも安産祈願のお参りは縁起は悪くない?

戌の日とは干支の戌と同じ12回に1回巡ってくるもので、干支が12年に一度なのに対し、戌の日は12日に一日の頻度で巡ってきます。
そして、妊娠5ヶ月に入って最初の戌の日に、神社へ出向いて安産祈願を行うことを『戌の日参り』もしくは『帯祝い』と言い、日本に古くから伝わる風習となっています。
お参りを行うのがなぜ戌の日なのかと言うと、犬は一度にたくさんの赤ちゃんを産み、しかも比較的お産が軽いことから、それにあやかって妊婦さんの出産も上手くいくようにお願いするためです。
神社に安産祈願に行くと腹帯を呼ばれるさらしのようなものを祈祷し、その場でお腹に巻いてもらえます。
なお、戌の日の安産祈願では六曜における縁起の良し悪しは気にする必要がありません。
先負であっても仏滅であっても特に問題がありませんが、大安と戌の日が重なると縁起がよいため、予約が混みあうことがあるようです。
戌の日に安産祈願へ行く時は妊婦さんの体調を第一に考え、体調が優れないようであれば無理はせず、次の戌の日に変更するなど柔軟に対応するようにしましょう。
安産祈願の日取りの決め方は?

安産祈願の日取りは、戌の日や六曜ではなく、妊婦さんの体調を最優先にして決めることが大切です。
一般的に妊娠5ヶ月に入ると、つわりが落ち着いて体調は安定しやすいと言われていますが、個人差があります。
また、前日まで何ともなくても、安産祈願を予定していた当日に急に体調不良になることもあり得るため、そのような時は無理をせずに予定を変更するなど、妊婦さんに負担のかからないスケジュールを組むようにして下さい。
安産祈願は縁起のよい日に行いたいという気持ちは理解できますが、赤口や仏滅であってもその日の体調がよいのであれば、縁起にこだわりすぎずに体調のよい日に行うようにしましょう。
安産祈願に向いている吉日は?

縁起のよい吉日と言えば大安が思い浮かびますが、大安以外にも次のような吉日もあります。
天赦日
神様がどのような悪事でも許すという意味で、この日は何をしても運勢がよい日とされています。
数ある吉日の中でも最高に縁起が良い日となりますが、一年に5日ほどしかない貴重な日となっています。
※天赦日について更に詳しい解説は、「天赦日の意味や由来と読み方!したほうがいいことは?」をご覧ください。
一粒万倍日
一粒の籾から万倍の稲が実るという意味があり、特に金運の運勢がよい日と言われていますが、安産祈願にもお勧めです。
※一粒万倍日についてさらに詳しく知りたい方は、「一粒万倍日とは?読み方やすると良い事は何?」をご覧ください。
母倉日
母が子を育てるように、天が人を慈しむ日という意味があり、特に婚姻関係が吉とされる日ですが、その意味から安産祈願の日取りとしてもよい日となっています。
※母倉日についての更なる解説は、「母倉日はいつ?すると良い事や仏滅と重なった場合は?」をご覧ください。
鬼宿日
鬼が宿にいて外を出歩かないため、何をしても上手くいく日という意味があります。
また、鬼宿日はお釈迦様の誕生日とも言われており、とても縁起のよい日となっています。
※鬼宿日については、「鬼宿日はいつ?意味や由来と読み方!」で詳しく解説いしています。
大明日
天が明るく万事を照らすという意味があり、何事も上手くいく日と言われています。
大安は都合が合わない時などは、他の吉日のお参りも考えてみると選択肢が増えてよいでしょう。
ただし、吉日と凶日が重なった場合(大明日と仏滅など)は、縁起のよい日とならないことがあるので注意して下さい。
※大明日については、「大明日の意味や由来と読み方!」で詳しく解説しています。
安産祈願は避けたほうがいい凶日は?

六曜には大安、友引、先勝、先負、赤口、仏滅の6つがあり、その中の大安、友引、先勝、先負が吉日、赤口と仏滅が凶日と言われています。
赤口は午の時刻(午前11時~午後1時)までは吉となりますが、仏滅は一日を通じて凶となるので、縁起が気になる方は避けた方がよいでしょう。
また、六曜以外にも凶日はあり、縁起が気になる方は安産祈願を行うのは控えるのがよいでしょう。
不成就日
何を行っても上手くいかない凶日と言われています。
※不成就日については、「不成就日とは?意味や由来と読み方や吉日と重なったらどうなる?」で詳しく解説いしています。
受死日
葬儀以外は大凶の運気となる日で、他のあらゆる暦注の中で最も縁起の悪い日とも言われています。
※受死日について「受死日の意味や由来と読み方!」で詳しく解説しています。
六曜と安産祈願との関係は?

六曜は中国が発祥の暦注の一つで、日本へは鎌倉時代末期から奈良時代に伝わったとされています。
六曜の起源については諸説ありますが、中国では賭け事が盛んに行われていたため、運勢を占うのに作られたと言われており、元は時間の吉凶を占うものだったと言われています。
それが日本に伝わった後、日の吉凶を占うものへと変化し、江戸時代になると庶民へと広く浸透していったと言われています。
このようなことから、六曜の発祥や起源には、安産祈願を行う神社や神道は何の関係もありません。
つまり、安産祈願の日取りを決める上で、六曜はそれほど重要視する必要はないというわけです。
縁起のよい日にこだわるあまりに、体調が優れないのに無理を押してお参りしてしまうと、お腹の赤ちゃんだけではなくお母さんの体も辛くなります。
六曜と安産祈願には関係がないので、あまり気にせずに予定を立てるのがよいでしょう。
先負の安産祈願は大丈夫?のまとめ
安産祈願は、大安などの六曜を気にして予定を立てるよりも、戌の日にお参りを行うのが昔からの習わしです。
そのため、戌の日が大安以外でも、気にすることなく予定を立てることができますが、安産祈願の日程は何よりも妊婦さんの体調を優先し、戌の日であっても体調が優れない時は無理をしないことが大切です。
また、戌の日や大安のお参りができない場合でも、友引は午前11時~午後1時以外、先勝は午前、先負は午後であれば縁起のよい吉日ですし、その他に天赦日や一粒万倍日など、縁起のよい日があります。
縁起を担いでお参りをしたいということであれば、このような日も候補に入れて考えてみるとよいでしょう。
先負の関連記事
先負に安産祈願のお参りをすると縁起が悪い?戌の日と重なった場合は?
先負に法事をしても縁起は悪くない?六曜で避けたほうがいい日は?
先負に宝くじを購入すると当たらないのは本当?買う時間帯はいつ?
先負に契約ごとは縁起が悪い?不動産や車の契約するのは大丈夫?
先負が開業日でも大丈夫なの?開業日の決め方はどうしたらいい?







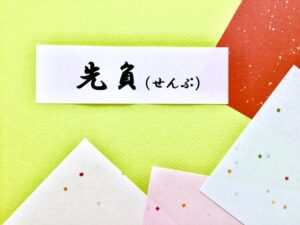



コメント